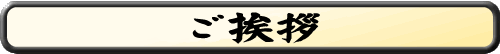
|
「八重の桜」再放送のお知らせ 「八重の桜」がNHKBSで毎週月曜日午後6時から放送中です。本作品は東日本大震災の3か月後に制作発表され、私も驚きました。東日本大震災後の混乱しているなかでの、スタッフ・キャストの皆様の頑張りには、心より敬意を表します。未見の方にはご覧いただければ幸いです。
白虎隊とは 会津藩の藩祖、保科正之(ほしな・まさゆき)公は、徳川二代将軍秀忠の庶子で、三代藩主正容(まさかた)公の時に松平姓を名乗るようになり、会津松平家は「御三家」につぐ「御家門」という家格を持っていました。 幕末、江戸幕府の力が衰えると、京都の治安の回復のために「京都守護職」が創設され、会津藩に白羽の矢が立ちました。藩内では「薪を背負って火を消しにいくようなもの」と反対意見が多数を占め、九代藩主松平容保(まつだいら・かたもり)公も固辞していましたが、幕府の重臣達は強引に会津藩に引き受けさせました。(文久2(1862)年) 会津藩は外交政策をめぐっての朝廷、幕府、諸藩の主導権争いに巻き込まれてしまったのです。 文久3(1863)年、急進攘夷派の長州藩と結びついた一部の公家の力が強くなりすぎたことを警戒した孝明天皇は、薩摩藩と会津藩に命じ、「八月十八日の政変」において、長州藩兵と一部の公家を京都から追放しました。 元治元(1864)年、「一会桑」(一橋慶喜、会津藩、桑名藩)勢力は、孝明天皇の支持のもと、「禁門の変」において、上洛してきた長州藩兵を退けました。 しかし、慶応2(1866)年、孝明天皇が急死すると、「一会桑」勢力に対する諸藩の不満が表面化し、会津藩は対幕強硬派の標的にされてしまいました。 慶応4(1868)年1月、大政奉還後の権力争いから、「戊辰(ぼしん)戦争」と呼ばれる国内を二分する大きな内戦になりました。薩摩藩、長州藩などの「新政府軍」と、会津藩、庄内藩、仙台藩などの「旧幕府軍」との戦いになりました。 会津藩の軍制は、フランスの軍制に習い年齢別に再編成され、中国の故事で方角の守護神とされていた空想上の動物の名前、玄武(げんぶ)、青龍(せいりゅう)、朱雀(すざく・しゅじゃく)、白虎(びゃっこ)を隊名につけました。 玄武隊(50歳以上)、青龍隊(36歳から49歳)、朱雀隊(18歳から35歳)、白虎隊(16,17歳)に大きく分けられ、さらに身分により高い方から、士中(しちゅう)、寄合(よりあい)、足軽隊に分けられました。 「白虎隊」は約340名おり「士中一、二番」「寄合一、二番」「足軽隊」の5隊に分かれていましたが、この中の「士中二番隊」42名が、慶応4年8月23日(太陽暦では10月8日相当)に、猪苗代湖近くの「戸ノ口原」で戦いましたが退却を余儀なくされ、うち20名が飯盛山に逃れてきましたが、(人数には諸説あり。他所での戦死者が飯盛山での自刃(じじん)者に含まれている模様)城下町で発生していた戦火を見て、もはや会津に勝ち目無し、敵の手にかかるよりはと、自刃しました。(理由には諸説あり)元号が「明治」に変わる16日前の出来事でした。 この時、飯沼貞吉だけが地元の人に助けられたため、この話が全国的に有名になりました。(「白虎隊」全体では85%にあたる290名が生き延びています)その後、籠城戦を1ヶ月戦いましたが、最終的には会津藩は降伏しました。 飯沼と同じ「士中二番隊」の隊士であった、酒井峰治(さかい・みねじ 1853~1932)の手記が、平成になってから公開されましたが(展示品案内参照)、酒井は生前当時のことは、家族にはほとんど語らなかったそうです。彼らは少年の日の深い心の傷を終生抱えていたのでした。
「士中二番隊」の行動については、生き延びた当事者の証言に食い違いが多い上に、当事者が明治中期以降の「白虎隊」に対する世間の評価に、かなり配慮している節があることから、現時点では断定的な物言いは避けるべきと、当館では考えています。 個人的には、「辰のまぼろし」(柴五三郎著・会津図書館蔵)の記述が、比較的事実に近いのではと考えていますが、、。大人の将校達は戦況不利と判断し、早い段階で退却命令を出したものの、納得がいかない一部の隊士が反抗したために、途中で(穴切村付近か)バラバラになったのではないでしょうか。飯盛山にたどり着いた白虎隊士は、おそらく一桁でしょう。 また、「白虎隊顛末略記」の筆者である原新太郎と、「士中二番隊」の原鋧三郎は別人です。(明治43年発行の名簿に別々の住所で載っています)失礼ながら、「白虎隊顛末略記」の記述の信憑性には疑念を感じています。飯沼貞吉の口が重いのにしびれを切らした原新太郎が、当時出回っていた出版物を参考に、話を膨らませたのではないでしょうか。 ところが一昨年、ある番組で「白虎隊顛末略記」を「新発見の飯沼貞吉の手記」と紹介していました。あの史料は17年前に発表されていて、「原新太郎の聞き書きに飯沼貞吉の朱書きが一部入ったもの」とでも称するべきで、最後のページには原の署名と花押まで書いてあり、「飯沼貞吉の手記」ではありません。さすがに看過できず、番組宛にメールを出しましたが、返信は来ませんでした。
飯沼貞吉が降伏後、長州に連れて行かれたという話も、懐疑的に見ています。会津藩士・山田善八が東京で謹慎している会津藩士の名簿を、明治2年11月に書き写した文書が当館にありますが、山田が謹慎していた「護国寺」のところに、飯沼時衛と貞吉の名前があります。 山田がその場にいない人物の名前をわざわざ書くとは考えにくく、脱走人の名前は別になっていますので、飯沼貞吉は父親と一緒に、ずっと東京にいた可能性があり、あの話を事実と断定してしまうのは危険です。 「楢崎頼三陣中日記」(萩市立図書館蔵)を読んでも、楢崎が国元に帰る時に、飯沼が同行していたとは思えません。(萩市立図書館のHPで、ログインなしで閲覧・ダウンロードできます) 現地には450万円かけて記念碑が建てられたそうですが、人違いや電信技師時代の話が間違って伝わっている可能性は本当に無いのでしょうか?マスコミには「美談」として、あたかも事実であるかのように取り上げられていて、大変困惑しています。 |
||||||
白虎隊記念館 館長 早川広行
|
||||||